
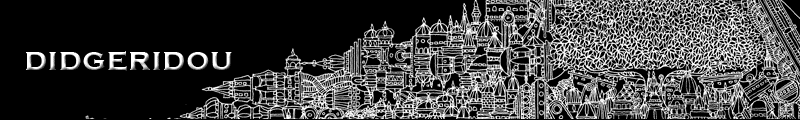
| 第26話「真のディジュリ道」 |
この頃になると、他のディジュリドゥプレーヤーの演奏を素直に楽しめるようになっていた。と言うのは、以前の僕はいつも人と競い合っていたからだ。あるディジュリドゥプレーヤーと出会うとしよう。すると吹き比べが始まるのだった。俺はこんな事もできる、こんな音も出せるぜという風にだ。これは僕だけではなく、オーストラリアにいた間、よく目にする光景だった。この事は、他の楽器に比べて特異な点ではないだろうか。まだ楽器としての世界的な認知度が低いという事もあってか、珍しい事をやっているという事だけに満足してしまって、肝心の音色という焦点からずれてしまっている状態から抜けだせない人が多い気がした。実際僕も、最初はそうだった。そんな人達には是非、本場オーストラリア、ダーウィンに行く事をお勧めしたい。世界中からディジュリドゥ、イダキの旅に出た人達が集まってきている。トラディッショナル、コンテンポラリー、色んなスタイルのディジュリストがそれぞれのディジュリ道を追い求め集まって来ている。オーストラリアにまで行って、ディジュリ道を追求しようという人間は、みんなそれなりに自分のスタイルを確立したいが為にやって来る。もしその地に3ヶ月、そして自分の培ってきたスタイルを正面から試す勇気があるのなら、遅かれ早かれそんなバトルのような事ばかりしていてもしょうがない事に気付くだろう。なにせすごい数のプレーヤーが集まって来ているのだから。犬も歩けばイダキに当たると言わんばかりである。へたすると、一日中ディジュリドゥバトルをしなければいけない。これはかなりきつい。少なくとも、僕にはきつかった。前方からディジュリドゥを担いだ奴が歩いて来るとしよう。やたらとお互いに意識しているのがわかるのだ。軽く挨拶を交わし、お互いにディジュリドゥに手を掛け、ケースから抜くのであった。まるで戦国時代の武士か侍の様である。そしてその戦いは演奏だけにはおさまらず、知識にまで及ぶのだった。お互いにうんちくを並べあうのだ。どこそこの族長はどうだこうだとか、誰々はこんな事を言っておりこんな事をしているなど。これにはいつもまいった。というか相手がまいっていた。英語があまりにも理解できていなかった為、勝負にならないのだった。いつも相手が僕の英語力に気付き、その場を立ち去って行くのだった。棄権勝ちだった。今から思うと、まるで近所のうわさ好きの主婦のようだ。だが、こんな事をいくらしていても真のディジュリ道には近付けないのだった。ここにどれだけ早く気付けるかである。一度自分を0(ゼロ)にする勇気がいるのである。ディジュリドゥ、イダキなる物はとても器が大きく、どんな自分も寛容に受け入れてくれる存在だと、僕は思っている。言葉やドレミが生まれる遥か昔から何一つ変わらぬかたちで現代まで受け継がれてきた世界最古の木管楽器であるこの存在は、遥か昔からこの地球、そして僕達人類の事を見守って来ているのだ。この音色はすべてをお見通しというわけかと思った時、今まで自信のなさを隠す為に、肩肘張っていちびっていた自分と向き合ってしまった。今まで培った価値観や社会観を一旦すべてゼロにし、この存在にすべてを捧げる覚悟を決めた。そして、たった一つの願い事をした。 |
(C)2008 JUNGLE MUSIC