
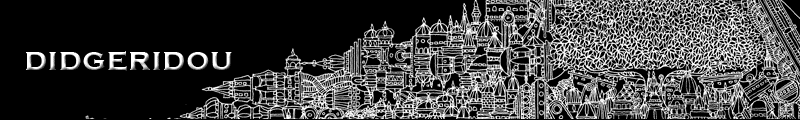
| 第5話「彼女の母」 |
ディジュリ道に入り、はや3年が経とうとしていた。ずっと独学で吹き続けてきた僕は壁にぶち当たっていた。このままでいいのだろうか?本場のプレーヤー達はどんな吹き方をしているのだろうか? CD屋に行ってもディジュリドゥの聞ける作品は数少なく、すでに何度も聞いた事のある作品ばかりだった。この先ディジュリドゥを極めるにはどうすればいいのだろうか?いろいろ考えてみた結果、日本におけるディジュリドゥに対する情報量の少なさとそこから生まれる間違った解釈や多くの誤解を本場オーストラリアに渡り自分の目と耳で確かめてくるという事だった。 この思いを彼女に伝え、すぐにでもオーストラリアへ行きたかった。だが、店の事を考えるとどうしても言い出せず、煮え切らない自分に腹立たしい日々を過ごした。そんなある日、彼女の母親が病気だと聞かされる。それもガンだというのだ。その日以来、彼女は母親の看病に付きっきりとなり、店にはほとんど来ない、来れない生活になった。もちろん服も全く作れなくなってしまった。その後、店の経営状態もどんどん悪化していった。すべてが中途半端になってしまっていた。義母の病状が早く良くなる事を願った。自分の力ではどうすることもできない大きな運命を感じながら時の流れに身をまかせる事しか出来ない自分が悔しかった。そんな中、彼女と話し合い店を閉める事になった。初めて味わった挫折だった。自分一人では何も出来ないまだまだ未熟な人間だという事を思い知った。これでいいんだと自分に言い聞かせるのが精一杯だった。 そんな中、義母の病状はどんどん悪化していった。そして「余命3ヶ月です。」と担当医からの宣告がなされた。僕は正直それまで人が死ぬという事について考えた事がなかった。一体どうすればいいのだろう。ただ一つ分かっている事はこんな事を考えている間も義母の病状はどんどん悪化していっているのだという事だった。何か義母にしてあげれる事、勇気付けられる事はないだろうかと考えた。彼女と 話し合いをして一つの決断を下した。それは娘の花嫁姿を見せてあげようという事だった。すぐ準備に取りかかった。式は義母に無理のないように、病院のすぐそばで行なわれた。ささやかな結婚式だったが久しぶりに義母の笑顔を見た。すごく嬉しそうだった。今でもその時の笑顔を思い出すと、自分のとった行動に間違いはなかったんだと勇気付けられる。その半年後、義母は静かに息を引き取った。四十九日の儀式を終えた時、彼女がこう切り出した。 「オーストラリア行って来ていいよ。ずっと行きたかったんやろ。」 と。確かにそうではあったが、母親の死後まだ心の整理もついていないであろう彼女を残して、行っていいものなのかどうかわからなかった。しかし、ディジュリドゥはというと、ずっと行き詰まったままだった。その頃、ディジュリドゥの話を彼女の前でする事はなかった。母親の看病の為に服作りを中段せざるをえなかった彼女にどこか後ろめたかったのだ。母親の死により、一まわりも二まわりも人間的に大きくなった彼女に見送られ、中途半端な状態では絶対に帰らないという決意と共にオーストラリア、ダーウィン行きの飛行機に乗り込んだ。 24歳、 夏の終わりの出来事だった。 |
(C)2008 JUNGLE MUSIC