
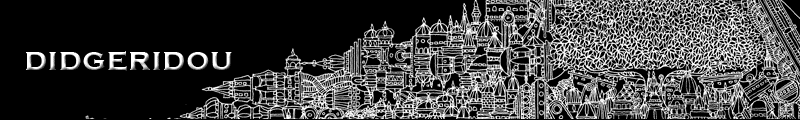
| 第6話「憧れの地」 |
英語が話せないという不安の中、なんとかボーダーチェックを済ませ、右も左も分からない様な状態でダーウィン空港に降り立った。時刻は朝の四時過ぎ。まだ真っ暗な夜空には大きな星が輝いていた。そこからバスでダーウィンシティへと向かった。まだ朝も早かったので, 店は何一つ開いていなかった。取りあえず、日の出とともに街をうろうろしてみる事にした。うわさどうりディジュリドゥの店がいっぱいあり、うれしさのあまり笑いが止まらなかった。これがこの場所の第一印象だった。しかし、今から思うとその時の僕とすれちがった人達は僕をクレイジーと思ったに違いない。朝早くから、ニヤニヤ笑いながら足早に街中うろうろ行ったり来たりしているのだから。 最初の1ヶ月は、毎日ディジュリドゥショップを回り、片っ端からディジュリドゥを吹いては気に入ったのがあると買ってバックパッカーへ持ち帰るという生活で、みるみる内に、持って行ったお金の大半が、ディジュリドゥへと変わっていった。 「このままやと来月には帰国せなあかん。ヤバイ。仕事探さな。」 と思い始めたのは、ダーウィン上陸後2ヶ月目の事であった。しかし、この田舎町ダーウィンで、当時英語の話せなかった僕にとって、仕事を探す事は容易な事ではなかった。 そんな重い気持ちの中過ごしていたある日、いつも遊びに行っていたディジュリドゥショップから働いてみないか、という話をもらったのだった。すごく嬉しい話なのだが一つ不安があった。その時、僕の英語力はというと、それはひどいものだったからだ。それでもいいのか、と何度も聞き返してみたのだが、答えはオーストラリア人らしく 働きだして1週間も経たない内に、その店を一人で見れというのだった。この時も何度も、俺の英語力で大丈夫かと聞いてはみたのだが、返ってくる答えはいつも「ノー、ウォーリーズ」だった。不安でいっぱいだったのだが、やってみると何とかなってしまうのであった。ディジュリドゥショップの店員は、一にディジュリドゥが吹けるという事が要求されるようである。とにかく、毎晩吹きまくった。吹いていると勝手に人が集まってくるのだった。きれいな夜空の下、マーケット中にディジュリドゥの音色が鳴り響いているのである。最高のセッティングだ。こっちから客に話し掛ける事はほとんどなかった。聞かれた事に適確なアドバイスをするのだ。その聞かれる内容というのは、だいたいみんな同じだったので、その答えとなる言葉を友達に書いてもらい、丸暗記したのだった。それらは主に、音の出し方、呼吸方、ケアの仕方、輸送の仕方についてだった。 |
(C)2008 JUNGLE MUSIC