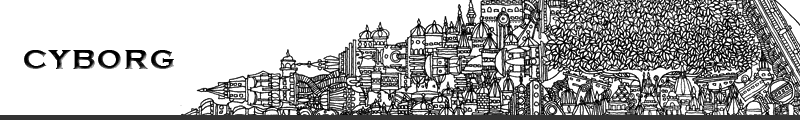Vol.2「CYBORG」につながってくるGOMAのキャリア総括
「CYBORG」のリリースから約2週間。既にその世界感にドップリつかっているリスナーの方も多いだろうが、このスペシャル・インタビューも早くも第2章が登場。第1章では、「CYBORG」制作の出発点からその世界観、またそれを凝縮したようなPV「Pulse」に込められたメッセージ、そして自身のルーツであるダンスとの出会いを語ってもらった。これまであまり語られなかったダンサー時代のエピソード、そして「身体が動くか動かないか」という当時の彼の音楽観からは、今作のキーワードの一つである「FRESH」という側面の一端が垣間見えたのではないかと思う。個人的には、「ダンス」やディジュリドゥの「呼吸」といった、ある意味「非」楽器的もしくは「超」楽器的な原体験を元に、作法や、慣習、常識といったフィルターを通さず、自らの身体に宿る感覚に忠実に向き合ってきたのが、GOMAというアーティストのエッセンスと思うのだが、どうだろう。
この話はまたの機会に譲るとして、この第2章では引き続き彼のキャリアを紐解きながら、「CYBORG」という一つの帰着点に至ったその道程を語ってもらった。まずは「CYBORG」の構想が生まれた、ロンドンから帰国後の02年頃の活動について聞いてみた。(なお、ディジュリドゥとの出会いやオーストラリアでの修行時代に関しては、HP内の「DIDGERIDOU」に詳しいので、そちらも参照されたし)
――前回の話から時系列的にはちょっと飛んでしまうんですけど、日本に活動の拠点を移した02年あたりは、ヒップホップとかレゲエ、ダブとかを強烈に原体験として持つ人たちとパーティーで共演してたじゃないですか? 今回のCYBORG」の音に関してもあの頃と延長線上で明らかに繋がっていると思うんですけど、当時そういう人たちとはどういう縁の中で一緒にやるようになったんですか?
ロンドン在住時の縁で繋がった人もいるし、イベントでたまたま一緒になって仲良くなったような人もいる。感覚としては、音の太さで繋がったのかもしれないね。ディジュもマイク通すとすごく太い音が出るから、そのバイブスが好きな人達が自然に集まって来たんじゃないかな。今も皆それぞれの道で元気にやってるし、たまに会ってもいいバイブスを共有できる大切な人達だね。縁としかいいようがないかな。そして、あの頃にやっていた事の延長が、今回のサイボーグに繋がっている。名義も、GOMA DA DIDGERIDOOを使ってるし。ディジュとオレの闘いみたいな感じだね(笑)。
今回の「CYBORG」の制作と密接な関係にある02年あたりのGOMA DA DIDGERIDOO名義での活動を経て、03年からはバリで出会ったガムランやケチャとのコラボレーションを音源として落とし込んでいく「バリ三部作」(『Jungle Champlu』『IN A JUNGLE』『ENDLESS WONDER』)と呼ぶべき作品群の制作に移行していく。「CYBORG」の持つカッティング・エッジな感覚とは一見、真逆の世界のようにも見えるが、その実「ヤバい」と感じたその自分の嗅覚に忠実に従う行動原理はどの作品でも不変であり、この作品群も単なる民族楽器同士のコラボと呼ぶには、あまりにもドープな世界観を擁している。
バリ島はオーストラリアのダーウィンから船で行ける場所だったし、オーストラリアにいく際にはガルーダ・インドネシア航空を利用して、必ずバリ島でオーバーステイのトランジットをしていた。最初はサーフィンをやるために海の方にステイしていたんだけど、ある時、寺院で初めてガムランを聞いて、吹きたい、いつかレコーディングしなきゃダメだって思って。ディジュリドゥもケチャも元は息だけから派生していて相性がいいはずだし、ケチャを聞いてて、低音が入ったらもっと楽しめるんじゃないかと思って。そして、03年に日本から機材全部持ち込んで、ウブドの山の方に簡易スタジオ造ってレコーディングを開始したんだ。MAC、POWER BOOK2台とPROTOOLS,LOGICにMACKIEという組み合わせだった。川沿いの宿屋を仲間で貸し切って1ヶ月間毎日納得いくまでやってた。夜、作業を終えると、川の流れる音が心地良くてすぐ眠りに入っていたのを思い出す。それと雨期で電源が安定しなくて、雨足が強くなるとすぐに電源が落ちてしまってやり直しを何回もした事も印象に残っている。バリでは、偶然友達に会ったりもしましたね。ブルーハーブのボスくんも、こんな場所で会うはずないでしょーっていうくらいの裏通りでご飯食べてたら普通に前から歩いて来たしね。で、そのままレコーディングに参加してくれて。俺はそういう自然な巡り合わせをメッセージだと捉えて今もやってますね。
時代ごとのタームでGOMAの活動を見てみるとき、通低音のように流れているのは、常に「ディジュリドゥの可能性を追求する」という探究心だ。この姿勢に一貫してブレがないのがGOMAのキャリアだと思うのだが、一方で、「その時その時感じているものを表現する」というナチュラルさが、作品の多様性を生み出している大きな要因だとも思う。それを支えるのが、感性レベルの要素と、もう一つ彼のリスナーとしての音楽的雑食性なのかもしれない。「CYBORG」を構成する音楽的イディオムも多彩を極めるが、ここではその構成要素をそれぞれ分解して理解すべく、個別のジャンルについて聞いてみた。
――ハウスとかテクノとかの4分打ちのキックを軸に展開されるいわゆるダンスミュージックとの出会いってどんな感じだったんですか?
オーストラリアのレイブ。トランスからミニマルまで、ダンスミュージック全般。四つ打ちって野外で聞いたらこんなに気持ちいいんだって発見した。90年代前半、大阪のロケッツというクラブで働いてた時に四つ打ちには触れていたんですけど、あえて自分がやろうって感じは無かった。そういう音の楽しさを自分の中で消化したのは、やっぱりオーストラリアのレイブで、97年かな。野外フェスっていうよりは、手作りのレイブっていう感じで。オーストラリアは土地が広いから、室内でパーティーをするっていう発想があまり無いみたいだった。もともと、BPM120以上の早いテンポの曲は踊れないっていうのが自分の中にあったんだけど、早いテンポには早いテンポに合うダンスがあるっていうのが見えてきた。やっぱりその頃でも、踊れるか踊れないかっていう(笑)。基本的にはベース、低音のグルーブがないと今でも踊れないんだけど・・・
当時自分が暮らしていたのはオーストラリアでも一番北のダーウィンっていう場所だったんだけど、そこは雨期と乾期の差がはげしくて、乾期はトラヴェラーや観光客も沢山来るんだけど、雨期は本当誰も来なくなるから、当時働かせてもらっていたディジュリドゥショップから休みをもらってケアンズからゴールドコースト、そしてバイロンベイへと東海岸を南下して行った。そしてバイロンの山のレイブでぶっ飛ばされた。テクノ、ハウス、そしてゴアトランス。ちょうど、その頃はゴアトランス全盛期だったのかな。「この音楽はなんや」って聞いたら、オージーの兄ちゃんに「お前、ゴアトランス、知らんのか」って言われたのを覚えてる。(笑)。
―(笑)あと、「CYBORG」の話で言えば、ヒップホップから始まって、ハウス、テクノ、レゲエっていう側面があると思うんですけど、レゲエに関してはどうだったんですか?
海外に出る以前から、レゲエは好きで聞いてたんですけど、基本UKものが多かった。JAH SHAKAが好きで、先輩のやってるレコード屋でSHAKAのサウンドシステムのテープ買って、そこで色々聞かしてもらっていた。アズワドやツインクルブラザーズ、ARIWA後はON-Uの周りをよく聞いていたかな。基本的にUKのカルチャーは、音楽やファッションなんかも含めて昔から好きだった。後、トラック制作をするようになってから、上物のネタで、ジャズは結構聞いた。ブルーノートの4000番台は特に聞いたかな。Lou Donaldson、Jackie Mclean、Art Blakeyなんかをよく聞いていたかな。基本、黒人音楽のグルーブが好きなんやろうね。
――そういうリスナーとしての幅広さもあるのかな、ナイト・ジャングルとかジャングル・リズム・セクションでも、GOMAさんのプレイヤーとしてだけじゃなくてコンポーザーというか、新しいアイディアを生み出す発案者っていう側面にもアルバムやライブを体験するたびに痺れます。いわゆるGOMAさんって中学生の頃からバンドを組んで、スタジオ通って、ライブハウス押さえてライブ、っていう道のりを歩んだ「バンドマン」ではないじゃないですか。ディジュリドゥという非西洋楽器に出会って、ある種事故的にミュージシャンとしての活動が始まったというか。 その分、逆にミュージシャンとしてこうあるべき、っていう常識、手癖みたいなのから自由なのかなっていう。
そうかも知れない。以前にGOMA&JRSのドラマーの椎野さんがインタビューで、「GOMAちゃんは、ドラマーの身体的能力を超えたもの要求してくる」っ言ってたんだけど(笑)。オレの言うアレンジやフレーズへのリクエストは暗号のように聞こえることもあるらしいし(笑)。でも、明確に自分の頭の中で鳴ってるサウンドがあって、それをどこまで再現できるのか、如何に現状を近づけるかっていう作業をオレは常にしている。自分の中に降りてくるサウンドを確実に音源に落とし込む作業。そして、それができているのは、周りにいるミュージシャンが素晴らしいからやと思うし、お客さんは勿論、メンバーやスタッフ、本当にみんなに助けられて今の自分が存在していると思う。
ここまで、作品や活動時期による作風の違いや、様々なジャンルの音楽との出会いを語ってもらっているわけだが、どの局面でも見受けられるのが「偶然という必然」とでも呼ぶべき感覚だ。自然な流れの中で出会ったアーティストや音楽と、その時の自分との化学反応を作品として落とし込んできたGOMAのキャリア。そこに作為的な要素は皆無なのだが、偶然に見える出会いも「CYBORG」への帰着という大きな流れの中では、ある意味では必然だったのではとも思える。
そして、ここから語られるのは、自分の感覚に素直に向き合ってきたGOMAが獲得した「陰と陽」「静と動」という感覚。これも、彼のキャリアを紐解く上で重要なファクターになっているようだ。
バリ三部作の流れでオーケストラでやるようになった頃から、一時期お客さんが完全に分かれた時期があった。ソロでやってた頃のお客さんは半分くらいになって、新しいお客さんが集まりだした。
――お客さんが離れるんじゃないかっていう予想,覚悟はあったんですか?
いや、そんな事は何にも考えてなかった(笑)。さっきと同じ話になるけど、頭の中で鳴ってる音をただ追っかけていただけ。その時その時、自分が感じているものを素直に嘘無く表現せなあかんと絶対に思っていて。人間は年齢や経験に応じて、目線や表現の感覚は自然と変わって来ると思う。前に見たモノを数年後もう一度見てみたら、全然違って見えたって経験、誰にでもあると思うんだけど、それって、全てのモノは変わり行くって事を教えてくれてる大切なメッセージだと思うんだよね。その場に居合わせた時の天候や光の加減でも違って見えてくるし、そのモノ自体も時の流れの中で風化しているから、自分の意識的なものや記憶の中では何一つ変わっていなくても、実際には全てのモノは常に変化し続けていて、その変化を受け入れるだけの許容力が自分の中に有るのか無いのかという世界ですよね。その感覚を大切にしたいし、その時々自分が感じて思ってるものを素直に恐れずに表現していきたい。
――『Million Breath Orchestra』前後のサイクルと、バリ三部作〜ナイト・ジャングル、ジャングル・リズム・セクションとかに帰着するようなサイクルがあって、二つの違うサイクルが一周してその一つの帰着点が、「CYBORG」を含めた2008年の一連のリリースなのかなっていう気がしているのですが。
そうですね。ナイトジャングル、ジャングル・リズム・セクションのバンドが始まって、一時期来なくなっていたお客さんが再びシンクロし始めて、再会した時に少し話したりすると、さっき俺が話した事、「常に自分が感じているものを、素直に表現して行くのが大前提にある」って事を、みんな理解してくれ出した感じでしたね。オレの活動って、1作品1作品にそれぞれのタームポイントはもちろんあるけど、全部実は繋がってるんですよね。ディジュリドゥを吹く時の呼吸法、循環呼吸(サーキュラー・ブリージング)じゃないけど、常に、陰(イン)と陽(ヤン)の組み合わせになってるっていうか。静と動っていうのもそうだし、旅と国内にステイしてるとかもそうだし。常に光と影みたいな感覚がある。影を見ると次は光を求めるし、光ばっかりだと次は影を自分の中に見る時間が必要になってくる。そのバランス感覚が自分は強いのかもしれない。まさに太陽と月の感覚ですね。
――その感覚を意識する様になったのはなぜ、いつ頃からだと思いますか?
それは、オーストラリアに住んで、大自然の中でデイジュを吹くようになって、自然と一体化するような感覚を見るようになった事が大きいかも。大自然の中で吹いていると、自分っていう存在がなくなって、呼吸だけが残る。呼吸が止まったらオレは死ぬんやなと思うようになって、身体の存在がなくなって、呼吸だけが続いているような感覚。その感覚を味わうようになってから、「動」とは又一味違う「静」の楽しさを自分の中に発見した。
――それを落とし込めるようになったのは、さっき話してもらったバリ三部作から?
バリ三部作のころは、「静」の曲を作るという試みもあったけど、あの当時はまだまだ、アグレッシブでしたね。「静」の部分を落とし込めたのは「Soul of Rite」からっていう気がしてます。子供ができたり、演奏のスキルやメンタル的な部分も備わってきて、全部のタイミングが一致したのがあの頃だったと思います。制作するのに、旅をしなかったんですよ。それまでは旅=制作って感じだったのに。日本で作品を作ろうって気分になった結果、あの作品が生まれたって訳です。数年前までは、ディジュリドゥも含め民族楽器や民族音楽はマニア向けというか、マイノリティな存在だったので、あのアルバムを何年か前にリリースしていたとしてもほとんど広がってなかったと思うんですよね。エコやオーガニックって言葉が浸透してきたのもここ数年だし、当時はまだそういったものに対して、世の中の偏見が残っていた時代でもあったんでイメージや意識、風潮を変えない限り次のステップは無いと思ってたんやよね。
以上、GOMA本人によるキャリアの振り返りで、「CYBORG」に辿り着いたその軌跡が多少なりとも見えてきたのではないだろうか。「CYBORG」を既にお手元にお持ちの方は、GOMAの言葉を反芻しながら今一度この作品に向き合っていただければ、「CYBORG」はまた違う世界観をアナタに提示してくれると思う。それだけ、「間口は広く、奥は深く」できている作品だから。
さて、次章では話もいよいよ佳境。「CYBORG」でGOMAが一番伝えたかったこととは?そんな部分に切り込んでいきます。
引き続き、お楽しみください!!
|