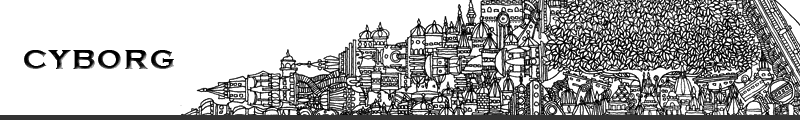Vol.1 「CYBORG」とPVの世界観、そしてダンス!
4月2日、ついにドロップされたGOMA da DIDGERIDOOのニューアルバム「CYBORG」。もう、みなさんはお手にとられただろうか?
ディジュリドゥから発生した一音一音を最新のテクノロジーを通じて、上物からベース、さらにはキック・ハット・スネア等の素材へと分解・再構築し、最新型のダンス・ミュージックへと昇華させるという前代未聞の取り組み。筆者は昨春、JUNGLE RHYTHM SECTIONの取材でGOMA本人にインタビューしているのだが、その時点で構想自体はそれとなく本人から聞いていた。そのときは、「じゃあ、ヒューマン・ビートボックスをディジュでやるみたいな?」なんて素っ頓狂な質問をした記憶があるくらい、正直、実際の音像をイメージできていなかったのだが。 それから約1年。「CYBORG」という名でリリースされた今回のアルバムは、果たして、筆者の想像を軽く超越したとんでもないブツとして手元に届いたのだった。
今回、「CYBORG」の全貌を解き明かすべく、再びGOMA本人に話を聞く機会を持つことができたわけだが、その模様を数回に渡って紹介していくスペシャル・インタビューの第一章をお届けする。今回は初回ということで、「CYBORG」の制作アイディアの出発点から、その世界観、また現在HPでも公開中のPV「Pulse」で披露した自身の表現のルーツとしてのダンスについて語ってもらった。
――今回のアルバムは着想としては、いつくらいからあったんですか?
2002年くらいかな。構想自体は、『Million Breath Orchestra』出してライブをやるようになって、そのソロのライブをやってるときに、アイディアが出て来て。持続音じゃない、単発の音みたいなのをディジュリドゥでつくれないかってところが最初。デイジュリドゥの音って基本的に「ブーーーッ」っていう持続音でしょ。持続音ではないところで隙間をつくりたいなと思って。ディジュリドゥのアタック音のところを切り取ってみたらどうなるんやろってところから「CYBORG」の発想は始まったかな。持続音をコンピューター上で切り取っていくと、「あれ、今のキックみたいな音? ハットもスネアも行けそうやん」っていうのが出てきて、「じゃ、これ一回外で鳴らしたらどんな音するんやろう」って感じで、クラブでのリハーサルのときとかに鳴らしてみたりした時に、「とんでもない発見をしちゃったよ、オレ」みたいな(笑)。ライブのサウンドチェックをするときに、ちょっとだけ何気なくブブっとやって、スピーカーの前にDATおいたりして(笑)。そうやってサウンドシステムで鳴らしたやつを家に持ち帰ってコンピューターに取り込んでっていうことを繰り返しながら、頭の中で鳴ってるサウンドに、自分がもっと近づくのには、コンピューターが絶対条件だな、というのが制作のスタートライン。
ーーディジュリドゥという世界最古の木管楽器と現代の粋を集めた最新のテクノロジーとの邂逅。そんな今作の最もコアな部分の着想は02年くらいから温めてきたアイディアだったとのことだが、それが制作面だけで語れるものではないことは、この特設HP内のGOMA本人による「CYBORG発売にあたって」を読んでもらっても理解してもらえると思う。「共存」というキーワードで語られるこのフィクションイメージとアルバムの音自体がまさに雄弁なのだが、さらに言えば、今作の最もユニークな点は、掲げているメッセージがそのまま実際の制作面に反映されている点だろうか。ディジュリドゥとテクノロジーの融合という物理的な手法を通して、現代が持つ危うげな側面に警鐘をならすと同時に、「共存」という解決策を形而上下を行ったり来たりしながらGOMAは提示している。
今回の方法論は何も制作面だけでの話ではなく、自然に残っているものとテクノロジーとがいい形のバランスでやっていかないと、先が見えてこないんじゃないかなって。ディジュリドゥが自然の部分で、コンピューターが都会やテクノロジーという仮定で表現してみた。これらをミックスしたら、こうなりますっていう良い部分もあるし、このままいったらこうなっちゃいますっていう警告的な部分ある。うまくバランスをとりつついかないと怖いことが起こるんじゃないかなっていう不安。当たり前のことを見なおす必要がある気もするしね。けど、別に難しいことを言ったりやったりする必要は全然なくて。次の世代を担っていく人たちにオレたちの信じるものを形にして伝えていきたい。
――そういうアルバムのタイトルに「CYBORG」ってつけたのは、どんなイメージだったんですか?
自然の生身であるディジュリドゥっていう楽器が、コンピューターでサイボーグ化されるっていう今作のイメージ。ディジュリドゥっていう楽器の、言ってみたらただの木の筒が発する生々しい音達が、コンピューターの中で再構築されて行く。その過程自体がすごいオレはサイボーグやなと思って。それでサイボーグっていう言葉が自分の中で何回もでてきてキーワードになっていった。テーマとか作り方自体もそのイメージで、PVはディジュリドゥを操る俺が最後の有機体として日々を過ごしていたがサイボーグ化していくというストーリーをPVディレクターの遠藤さんからいただいて。だから、あのボディーペイントは、サイボーグのイメージ。
ーー今後アップされていく第2章以降にも、より深く掘り下げて語られる今作の「共存」というコア・イメージだが、GOMA自身も語っている通り堅苦しく考える必要は、まったくない。まずはこの音の世界を純粋に楽しんでもらうことが先決なのだが、とっかかりとして是非チェックしてもらいたいのが「PULSE」のPV。近年のファンにはあまり知られていないかもしれないが、そもそもGOMAはディジュリドゥに出会う前、ディジュリドゥプレイヤーとして活動を始めたのと同じ約10年間、関西圏のダンサー達にいまなお語り継がれている「ともだち」というクルーで活動をしていた。このPVで披露されたGOMAのダンスに目を奪われた方も多いのではないだろうか。「CYBORG」はかなり重層的な構造になっているのだが、アルバムのもう一つの側面であるFRESHかつFLESHな感覚を紐解くべく、PVのイメージとダンスやヒップホップとの出会いを聞いてみた。
もともと、ダンスをやってた頃も含めてのこれまでの過程と今作のイメージをつなげるようなPVをつくりたいってことで、どういうものをつくろうかっていうときに、自分が何かしら動くっていうのがいいんじゃないかと、例えば1カット、1カットを撮影してつなげていくような感じ、サンプル画像とか見ながらイメージ作りしてみたけど、イマイチ。ダンス取り入れたらオモろいっていうのは、イメージとしてあったけど、自分の身体と相談してみたら「できんの、そんなん?」みたいな(笑)PV撮影するって決まってから、「10周年だし、今回のアルバムは今までのことをいい感じでミックスできてるよね」っていう話をしてたら、スタッフからも「久々に踊ってみるのは?」って言われてやっぱり踊るしか無いのかと(笑)
――(笑)そもそも、GOMAさんにとって、ダンスとかヒップホップとの出会いって、いつごろで、どういう存在だったんですか?
いまから思うと、最初の出会いは小学校5年か6年のときに見た風見慎吾さんのブレイクダンスかな。そこから、たまたま小学校のときに仲のよかった友達の兄貴がダンスをやってて、家に遊びに行ったときにそのビデオを見せてもらって、オモろいなーってハマりだして、って感じ。
――それは、生まれ育った大阪・泉州での話ですよね? 泉州はそういう環境に恵まれていたんですか?
そうかも知れない。たまたま周りにそんな情報があった感じかな。商店街で変わった盆踊りみたいなのが鳴ってて、お店の兄ちゃんと話してたら「ボブ・マーリーやで」って教えてもらったのを覚えてる。岸和田のだんじり祭だったりカルチャーが色濃い地域やから、集まって踊ったりスケートしたりみたいなカルチャーも育ちやすかったのかも知れない。
――当時は、どんな音で踊ってたんですか?
エレクトロみたいな感じかな。シュガーヒル・ギャングとか、ハービーハンコック「ROCK IT」とか、バンバータとか。85、6年かな。他の音楽とかはあんまり知らなかったし、たまたま周りにいた人達がそういうのを聞いてて、ダンスするのにそういうビデオとかで流れてる曲が聞きたくなるやん? だから、そういうのを真似して、それを聞いて踊りの練習をする。で、その中にRUN DMCとか出てきたり、ボビー・ブラウンとかのニュー・ジャック・スイングとかの時代があって。音に興味持ち出して聞き始めたのは、ボビー・ブラウンとか、その辺の時代からやし。それまでは友達の兄貴とかにコピーしてもらったテープをラジカセに入れて持ってって、とにかく踊る。そういう感じやった。
で、途中でスケートとかがだんだん流行ってきて、そのなかから、みんなスケートいくやつはスケートいって、絵描くやつはそっちに走って、分かれていったね。チームの中からスケーターになるやつもおれば、グラフィティにいくやつもおれば、MCになるやつもおったし。
――当時ダンスにのめりこんでいくなかで、それ用の音とか自分でつくったりしてたんですか?
いや、ミックステープ的なものは早い段階から作ってたけど本格的に音作りを始めたのはダンスの後かな、あの当時は、ダンスバトルが主流やったから音を作るよりも、マシーン原田さん(現DANCE DELIGHT主催)達が踊ってたパーティーとかに遊びに行って必死にダンス覚えてたって感じだった。マシーンさんがリーダーを勤めていたエンジェルダストブレイカーズ(日本のブレイクダンスの歴史を語るとき欠かせない代表的なブレイクダンスチームの一つでナインティナイの岡村隆史が所属していた事でも有名)というチームがとにかくすごかったから、それ見たさに通ってたね。そして丁度その頃に「元気が出るテレビ」のダンス甲子園に、よく一緒に踊ってた岸和田のトラッシュなんかが出始めて、しばらくダンスのちょっとしたブームが来た感じだった。オレ達もその頃に「ともだち」ってチームを組んでいて、アキラさん(CRAZY-A)やチノさん達が審査員で来る大会があるから出てみようってなって出たら優勝した。その大会が今や日本を代表するDANCE DELIGHTの第一回目で。たまに年下のダンサーの子達に会うことがあって話するとびっくりされる。けど、話すと必ず「踊って!」みたいに言われるから海外から帰って来てからは言わない様にしてた。(笑)
高校の頃は、GM YOSHIさんやDJ BEATさん達がDJするパーティーにダンスしにいったり、18歳になって仲間が免許取ると車で8時間掛けて横浜、六本木のサーカスに踊りに行ったりして、よく車で寝たりしてたなー。そこでZOOのヒロさん(現Exile)やサムさん、オウジさんのダンス見て刺激受けて帰ったり、KRUSH POSSEってグループでミヤジさんやタケジさん達が踊るって聞いては見に行ったり。今から思うと主催してたのがDJ KRUSHさんだったみたいな。やっぱ東京は違うなーって衝撃だった。その頃は千日前の「サーカス」っていう小さいけどガラス張りでセンスの良いダンサー達が集まるクラブがあってよくそこで踊ってた。しばらくして吉本興行の人達と仲良くなって、当時吉本が営業していた「ベイサイド・ジェニー」とか「デッセ・ジェニー」でSHOWをしないかって話になって定期的にやらせてもらう様になっていったかな。そのころつくってたミックステープは、EPMDとか Gang Starr、Digital Undergroundとかやったね。
――じゃあ、音的には、バンバータから、RUN DMC、そしてGang Starrまで、ある種ヒップホップの創世記をブレイクダンサーとして体験してきたんですね。
そう。オレにとっては全部一緒、要は身体が動くか動かへんか、それだけで考えてた。「音楽=ダンスをするためのもの」みたいなね。完全にダンス・ミュージック。で、もっと後になって「静と動」みたいなそっちの楽しみも、旅とかするようになってわかってきたけど、そのときは完全に音楽=ダンスで、身体が動く動かへんか腰に来るか来ないか、という感じやったね。でも今回のPVは、人に見せるダンスっていう意味では、ホントに久しぶり。撮影の次の日はめちゃくちゃ筋肉痛やったし(笑)。パーティーとかにいって軽く踊るっていう感覚はあったけど、実際に見せれるものとして踊るっていうのは、10何年やってなかったから。
――じゃあ、撮影前もトレーニングを積んで、みたいな?
もう、トレーニング。フリがどうこうっていうよりも、まずそこから、みたいな(笑)。最初は、フリの段階からやってみたんだけど、まったく身体は動かないし、体力的にも全然続かなくて。だから、まず筋肉を目覚めさせるところから始めた。で、撮影日が近づいて来るにつれて、自分の身体の動かなさにどんどんヘコんで、すごいブルーになって、撮影前日に、「オレ、明日、あかんかも・・・」って(笑)
結果的には、自分の思い描いてた世界観が出てる良いPVが出来たんとちゃうかなって満足してる。身体の方もなんとか撮影が進むに連れていい感じに動いていってくれたしね。久々にダンスしてみて、「ダンスやってた時代の自分も、ディジュリドゥをやってきた自分も俺なんや」って・・・自分の通ったルーツは代えられへんし、結局自分の経験してきたものだけでモノ言ったりやったりしないと、説得力がないんだよね。上っ面だけのものだと、何年か後になくなっちゃってるっていうか。
PVで最後のシーンに出てくる子どもの手は、バランス感。自然があってコンピューターや都会があって、そのバランス感をうまいことやっていかないと次の世代につながっていかないんだよということが、伝えたくて。アルバムのテーマでもあるんだけど。次の世代の象徴である子どもの手が出てきて、オレらが生きてきた世代で培った知識を次の世代に繋いでいきたいっていう、イメージかな。
この第一章で、「CYBORG」の世界観の断片は感じていただけただろうか。第二章以降では、GOMAのキャリアを総括しながら、今作のテーマに辿り着いたその軌跡を辿っていく予定なので、こまめにチェックされたし。
お楽しみに!!